ボルボのオーナーにとって、定期的にやってくる車検は少し気になるイベントかもしれませんね。そろそろ車検のタイミングが近づいてきて、今回の車検費用はいくらくらいかかるのだろう、と考える方も多いと思うんです。
特に、安心感を重視して正規ディーラー車検に任せるべきか、それともコストを考えて民間車検を選ぶべきか、選択肢はいくつかあります。中には、ユーザー車検に挑戦してみようかと考えている方もいるかもしれません。
また、法定費用のように必ずかかるお金もあれば、ボルボならではの特別な点検項目も気になるところ。具体的な金額を知るためには事前の車検見積もりが欠かせませんし、車を預けている間の代車サービスも生活によっては大切になってきます。
この記事では、そんなボルボの車検に関するさまざまな疑問を一つひとつ解消していきます。
- ボルボの車検にかかる費用の内訳と相場
- ディーラーと民間工場のメリット・デメリット
- 具体的な点検項目と費用の関係性
- 車検費用を賢く抑えるための選択肢
ボルボの車検、費用の内訳と基礎知識
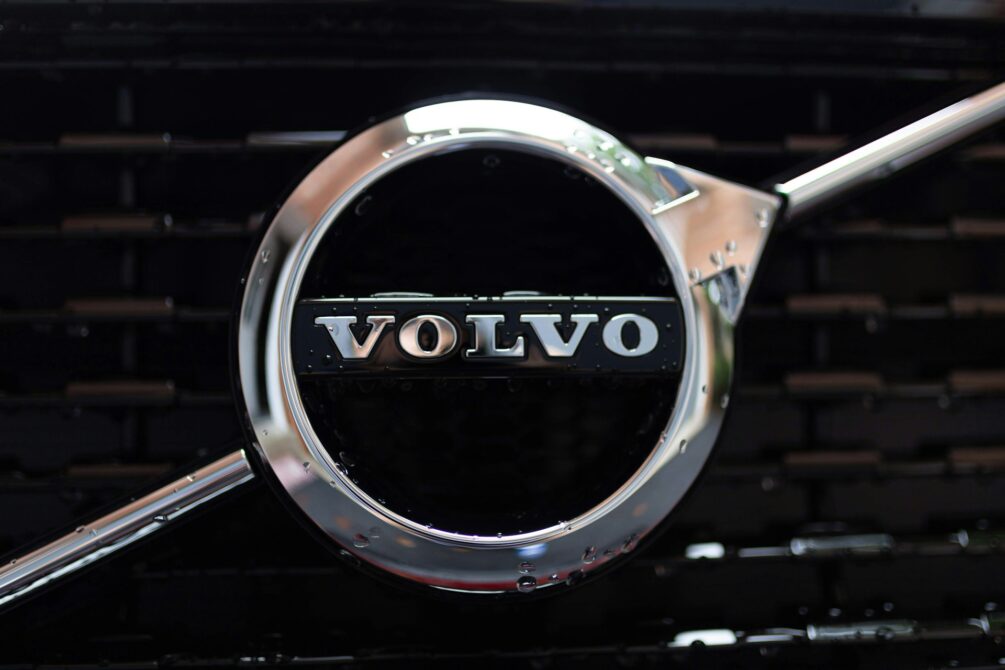
- 知っておきたい車検のタイミング
- 車検費用の総額はいくらになる?
- 内訳①:国に納める法定費用とは
- 内訳②:ボルボ独自の点検項目
- 正確な金額は車検見積もりで確認
知っておきたい車検のタイミング

ボルボの車検を受けるタイミングは、日本の法律で定められている他の車と基本的に同じです。新車登録をしてから最初の車検は3年後、それ以降は2年ごとに受けるというサイクルになっています。これは、車の安全性と環境性能を定期的に確認するための大切な決まりごとです。
車検は、車検証(自動車検査証)の左下に記載されている「有効期間の満了する日」までに完了させる必要があります。多くの場合、この満了日の1ヶ月前から受けるのが一般的だと思いますが、2025年4月1日以降は『2か月前』から受検しても次回満了日は短縮されません。焦らずに計画を立てられるこの期間を利用するのがおすすめです。
もし、うっかり満了日を過ぎてしまうと、その車は公道を走ることができなくなります。気づかずに走行してしまうと、道路運送車両法違反となり、厳しい罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金、そして免許の違反点数6点による免許停止処分)の対象となる可能性があります。
車検の有効期間は、フロントガラスの中央上部に貼られている検査標章(車検ステッカー)でも確認できますので、車検証と合わせて定期的にチェックする習慣をつけておくと、より安心かもしれませんね。
車検費用の総額はいくらになる?

ボルボの車検費用と聞くと、少し高価なイメージがあるかもしれませんが、実際の金額は依頼する場所や車の状態によって大きく変わってきます。大まかな目安として、10万円台前半で済むこともあれば、大規模な部品交換が必要になると20万円以上になることも珍しくありません。
この費用の内訳は、大きく分けて「法定費用」と「車検基本料・整備費用」の2つから成り立っています。
法定費用は、税金や保険料なのでどこで車検を受けても金額は変わりません。一方で、車検基本料や整備費用は、依頼先の方針や技術料によって差が出てくる部分です。
例えば、年式が新しく走行距離も少ないボルボであれば、交換が必要な消耗品も少なく済むため、費用は抑えられる傾向にあります。逆に、製造から年数が経っていたり、走行距離が10万km近くになっていたりすると、タイミングベルトやブレーキ関連部品といった高額なパーツの交換が必要になることも。そうなると、総額が大きく変わってくることも考えられます。
このように、車のコンディションが費用に直結するため、一概に「ボルボの車検はいくら」とは言えないのが実情です。
内訳①:国に納める法定費用とは
ボルボの車検費用を考えるとき、まず押さえておきたいのが「法定費用」の存在です。これは、車検を依頼するお店に支払う整備料金とは全く性質が異なり、いわば法律にもとづいて国や保険会社に納める公的な費用のこと。そのため、正規ディーラーに頼んでも、近所の民間工場に頼んでも、あるいは自分で検査場に持ち込むユーザー車検であっても、この法定費用だけは金額が変わることはありません。
言ってしまえば、車検費用全体の「値引きできない固定費部分」と考えると分かりやすいかもしれませんね。この法定費用の内訳は、主に「自動車重量税」「自賠責保険料」「印紙代」という3つの項目で構成されています。一つひとつ、もう少し詳しく見ていきましょう。
自動車重量税:車の重さに応じてかかる税金
自動車重量税は、その名の通り、車の重量に対して課される国税です。車両が重いほど道路に与える負荷が大きい、という考え方に基づいているため、重量が重いモデルほど税額は高くなる仕組みになっています。
ボルボのラインナップは、堅牢なボディ構造を持つモデルが多いため、車両重量が1.5トンを超えるケースがほとんどです。例えば、人気のSUVであるXC60などは、グレードによって1.8トン前後になることもあります。
この税額は、0.5トンごとに区分が分かれており、さらに新車登録からの経過年数によっても変動します。長く乗っている車ほど税額が上がるのが特徴で、「13年経過」と「18年経過」のタイミングで段階的に高くなります。
| 車両重量 | 12年まで | 13年経過後 | 18年経過後 |
| ~ 1.5トン | 24,600円 | 34,200円 | 37,800円 |
| ~ 2.0トン | 32,800円 | 45,600円 | 50,400円 |
| ~ 2.5トン | 41,000円 | 57,000円 | 63,000円 |
※上記は2年自家用の場合の税額目安です。
ただし、これを少し複雑にしているのが「エコカー減税」という制度です。ボルボのRechargeモデルのようなPHEV(プラグインハイブリッド)やBEV(電気自動車)は、環境性能が優れているため、このエコカー減税の対象となります。
多くの場合、新車登録後、初めての車検時には重量税が100%免除(0円)になることが多いです。これは非常に大きなメリットと言えるでしょう。ただ、2回目以降の車検では通常の税額に戻ることがほとんどなので、その点は覚えておくといいかもしれません。
自賠責保険料:すべての車に加入が義務付けられた保険
自賠責保険は、「自動車損害賠償責任保険」の略称で、法律によってすべての車に加入が義務付けられているため「強制保険」とも呼ばれます。車検を受ける際には、次の車検満了日までの期間(通常は24ヶ月分)の保険料をまとめて支払う必要があります。
この保険の最も大切な役割は、交通事故の「被害者救済」です。万が一、対人事故を起こしてしまった場合に、被害者の治療費や慰謝料など、人に対する損害を最低限補償することを目的としています。
ここで注意したいのは、補償範囲はあくまで「対人」に限られるという点です。つまり、相手の車の修理代や、自分の車の修理代、電柱などの物損、そして自分自身のケガなどについては、一切補償の対象外となります。だからこそ、ほとんどのドライバーは、この自賠責保険ではカバーしきれない範囲を補うために、別途「任意保険」に加入しているわけです。
保険料は、車種や年式、ドライバーの年齢などに関わらず、自家用乗用車であれば一律の金額です。2025年9月時点では、24ヶ月契約で17,650円となっています。
印紙代:検査や手続きのための手数料
印紙代は、車検の検査や、新しい車検証を発行してもらうために国(運輸支局)へ支払う手数料です。少しややこしいのですが、この印紙代は、車検を依頼する工場の種類によって金額が数百円程度異なります。
工場の種類は、大きく「指定工場」と「認証工場」の2つに分けられます。
- 指定工場
- 厳しい基準をクリアし、自社工場内に車検の検査ラインを持つことを国から認められた工場です。ここでは整備から検査までを一貫して行えるため、「民間車検場」とも呼ばれます。手続きがスムーズで、印紙代も比較的安く、2025年時点では1,800円(電子申請の場合)が一般的です。
- 認証工場
- 分解整備を行う許可は得ていますが、検査ラインは持っていません。そのため、整備が終わった後、車を国の運輸支局へ持ち込んで検査を受ける必要があります。この場合、国の検査ラインを使用する手数料などが加わるため、印紙代は指定工場より少し高く、2,300円程度になることが多いです。
ボルボの正規ディーラーは、その多くが「指定工場」の認可を受けていると思います。
これらの法定費用を合計すると、例えば「初度登録から5年経過した、車両重量1.8トンのエコカー減税対象外のボルボ XC60」の場合、自動車重量税(32,800円)+自賠責保険料(17,650円)+印紙代(1,800円)で、合計52,250円が最低でも必要になる、という計算になります。これが、車検費用の揺るがない土台となる金額です。

内訳②:ボルボ独自の点検項目

車検の費用が「法定費用」と「整備費用」に分かれることは、前述の通りです。ここでは、その整備費用の根拠となる「点検」の内容について、もう少し深く掘り下げてみたいと思います。車検の際には、まず国が定めた最低限の安全基準をクリアしているかを確認するための、法的な点検が行われます。
車検の土台となる「法定24ヶ月点検」
これは一般的に「法定24ヶ月点検」と呼ばれ、文字通り法律で定められた点検項目をチェックするものです。自家用乗用車の場合は、ブレーキの効き具合やパッドの残量、エンジンオイルの漏れ、ドライブシャフトブーツの破れといった基本的な項目から、ステアリング装置やサスペンションの状態、排気ガスの濃度測定まで、合計60項目にわたって行われます。
言ってしまえば、これは日本国内を走行するすべての車に課せられた、安全性を担保するための「共通の基礎体力測定」のようなもの。どこの工場で車検を受けても、必ずこの点検は実施されます。
ボルボの真価を維持する「独自のプラスアルファ」
しかし、ボルボの正規ディーディーラーで行われる車検は、この法定点検だけで終わりません。法定点検が「現在の車が最低限の安全基準を満たしているか」を確認するものであるのに対し、ディーラーの点検は「未来の安全性と快適性を予測し、ボルボ本来の性能を維持する」という視点が加わります。その中核を担うのが、「IntelliSafe(インテリセーフ)の点検」と、専用診断機「VIDA(ヴィーダ)」による診断です。
ボルボの頭脳と眼を司る「IntelliSafe」の点検
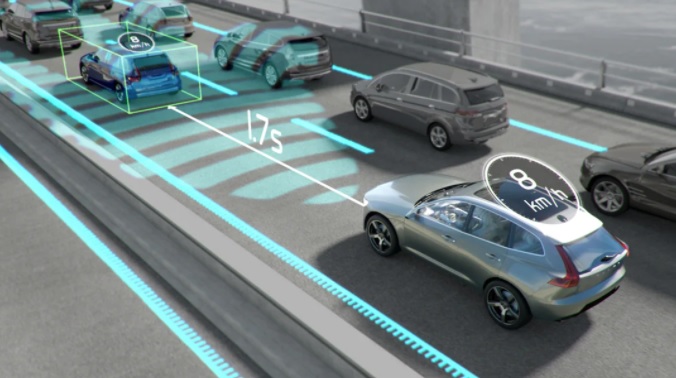
IntelliSafeは、衝突被害軽減ブレーキをはじめ、ボルボの安全思想を具現化する先進安全・運転支援技術の総称です。これは、もはや単なる機械ではなく、車に搭載された「賢い頭脳と鋭い眼」と言えるかもしれません。このシステムが100%の性能を発揮するためには、非常に精密な点検が不可欠です。
例えば、フロントガラスに装着されたカメラやフロントグリル内のレーダーは、ミリ単位のズレも許されません。もし飛び石などでガラスを交換したり、軽い接触でバンパーがズレたりすると、センサーが検知する距離や角度に誤差が生じ、いざという時にシステムが正常に作動しない可能性があります。
ディーラーでは、専用の測定器やターゲットを用いて、これらのセンサーやカメラの調整(エーミング)を精密に行います。また、後方の死角を監視するBLIS(ブラインドスポット・インフォメーション・システム)や、後退時の安全を確保するCTA(クロス・トラフィック・アラート)といった機能についても、センサーの状態を細かくチェックします。
車と対話する診断機「VIDA」の活用
VIDAは、ボルボ車のために開発された専用のコンピューター診断システムです。これは単にエラーコードを読み取るだけでなく、いわばボルボの電子システム全体と「対話」するための重要なツールです。
整備士がVIDAを車両に接続すると、目視では決してわからない数百ものセンサーの稼働状況や、電子制御ユニットの状態をリアルタイムで把握できます。これにより、今はまだ表面化していない不具合の兆候を早期に発見し、大きなトラブルに発展する前に対処する「予防整備」が可能になります。
そして、VIDAが持つもう一つの非常に重要な役割が「ソフトウェア・アップデート」です。現代のボルボは「走るコンピューター」とも言えるほど、多くのソフトウェアによって制御されています。ボルボ本社は、車の発売後も、燃費性能の向上、変速ショックの低減、インフォテインメントシステムの安定性向上、そしてIntelliSafeの認識精度向上など、さまざまな改善を目的としたソフトウェアを継続的に開発・配信しています。
この最新のソフトウェアは、ディーラーのVIDAを通じてインストールできます。つまり、ディーラーで車検を受けることは、愛車の頭脳を常に最新の状態にアップデートし、購入時よりもさらに洗練された性能を引き出す機会にもなるのです。
このように、ボルボ独自の点検項目は、法定点検という土台の上に、ブランドが誇る安全性能と快適性を未来にわたって維持するための、いわば「付加価値」と言えるでしょう。この手厚い点検内容が、ディーラー車検の費用に含まれていると考えると、その価格設定にも納得がいくかもしれませんね。

近年のGoogle搭載モデルはOTA(無線)アップデートにも対応しています!
正確な金額は車検見積もりで確認
最終的にどれくらいの費用がかかるのかを正確に知るためには、やはり事前に車検見積もりを取ることが何よりも確実な方法です。多くのディーラーや整備工場では、車検満了日の数ヶ月前から無料で見積もりを受け付けています。
見積もりを依頼すると、法定費用に加えて、どのような点検や部品交換が必要で、それぞれにいくらかかるのかが記載された見積書が提示されます。ここで大切なのは、提示された整備項目の一つひとつについて、その内容をしっかり確認することです。
例えば、交換を推奨されている部品が、「今すぐ交換しないと安全に関わるもの」なのか、それとも「現時点では問題ないが、次の車検までには交換した方が安心できるもの(予防整備)」なのかを質問してみると良いでしょう。
もし内容に少しでも疑問があれば、遠慮せずに担当者に質問することが納得のいく車検につながります。可能であれば、2〜3ヶ所の店舗で見積もりを取って、内容と金額を比較検討する「相見積もり」を行うのも、費用とサービスのバランスを見極める上で非常に有効な手段だと思います。
ボルボの車検、依頼先の選び方と比較

- 安心と信頼の正規ディーラー車検
- 費用を抑えられる民間車検のメリット
- 自分で通すユーザー車検の方法と注意点
- 意外と重要?代車サービスの有無
- 満足のいくボルボの車検を受けよう
安心と信頼の正規ディーラー車検

ボルボの正規ディーラーで車検を受ける最大のメリットは、他にはない圧倒的な専門性と、それに裏打ちされた安心感にあると思います。ディーラーに在籍する整備士は、ボルボの車を専門的に扱うためのトレーニングを積んだプロフェッショナルであり、各モデルの構造や特性、そしてウィークポイントまでを深く理解しています。
正規ディーラーのメリット
工場には、前述した専用の診断機「VIDA」や、特殊な工具が完備されています。これにより、複雑化する一方の電子制御システムや安全装備の隅々まで、的確に点検・整備することが可能です。また、定期的にメーカーから配信される最新のサービス情報や、リコールには至らないまでも改善対策が必要な「サービスキャンペーン」の情報なども、ディーラーであれば確実に対応してもらえます。
交換部品が必要になった場合も、品質が完全に保証されたボルボ純正パーツを使用するため、車が持つ本来の性能を長く維持できるという大きな安心感があります。そして、整備記録(整備記録簿)がしっかりと残るため、将来的に愛車を売却する際の査定評価で有利に働く可能性が高いのも、見逃せないポイントかもしれません。
注意点やデメリット
一方で、デメリットとして挙げられるのは、やはり費用の面です。車検基本料や部品代、そして整備にかかる時間あたりの工賃(レバーレート)などが、民間の整備工場と比較して高めに設定されているのが一般的です。ただ、その価格には、質の高いサービス、専門的な技術、そして何物にも代えがたい安心感という価値が含まれている、と考えることもできるでしょう。
費用を抑えられる民間車検のメリット

車検にかかる費用を少しでも抑えたい、と考えるのであれば、民間の整備工場や車検を専門に扱うフランチャイズ店などが有力な選択肢になります。
民間車検のメリット
最大のメリットは、言うまでもなく費用の安さです。ディーラーよりも車検基本料が低く設定されていることが多く、整備費用を抑えるための工夫がしやすい点が魅力です。
例えば、部品交換が必要になった際に、純正パーツだけでなく、同等の性能を持つより安価な「社外品(OEM品など)」や、中古部品を修理・整備した「リビルト品(再生品)」などを選択できる場合があります。これらのパーツを賢く利用することで、車検の総額をかなり抑えることが可能です。
また、地域に根ざした工場であれば、オーナーの要望に柔軟に耳を傾けてくれることも多く、予算に応じた整備プランを相談しやすいという側面もあるかもしれません。
注意点やデメリット
ただ、工場によって技術力や設備の充実度にばらつきがある点は、事前に理解しておく必要があります。特に、ボルボのような構造が複雑な輸入車は、専用の知識や診断機がないと対応できないトラブルも考えられます。依頼する前には、その工場のウェブサイトで輸入車の取り扱い実績が豊富かどうかを確認したり、「ボルボの車検も大丈夫ですか?」と直接問い合わせたりして、安心して任せられるかを見極めることが大切です。
ここで、ディーラー車検と民間車検の特徴を表で比較してみましょう。
| 項目 | 正規ディーラー車検 | 民間車検 |
| 費用 | 高めの傾向 | 安めの傾向 |
| 専門性 | 非常に高い(ボルボ専門) | 工場による(得意・不得意がある) |
| 使用部品 | 純正パーツが基本 | 純正・社外品・リビルト品など選択可 |
| 安心感 | 非常に高い | 工場の実績や評判による |
| 柔軟性 | マニュアル通りの傾向 | 相談しやすい場合がある |
| 整備記録 | プラス査定の可能性あり | 工場による |
自分で通すユーザー車検の方法と注意点

整備に関する一定の知識や経験がある方であれば、自分で運輸支局などに車を持ち込んで検査を受ける「ユーザー車検」という方法も選択肢の一つです。
ユーザー車検のメリット
この方法の最大のメリットは、何と言っても費用の圧倒的な安さです。業者に支払う車検基本料や点検料、代行手数料が一切かからないため、支払うのは法定費用と、もし必要であれば自分で交換した部品代、そして少額の書類作成費用だけで済みます。大きな整備が不要な状態であれば、総費用を法定費用+数千円程度に抑えることも可能かもしれません。
挑戦する上での注意点
しかし、これは誰にでもおすすめできる方法ではないのが実情です。まず、検査が行われるのは平日の昼間のみなので、そのために仕事を休むなどして時間を確保する必要があります。事前にインターネットでの予約が必須で、当日は車検証、自賠責保険証明書、自動車納税証明書といった多くの書類を自分で準備しなくてはなりません。
検査ラインでは、係員の指示に従って自分で車を操作し、ブレーキの効き具合、ヘッドライトの光軸、排気ガスの濃度などをチェックされますが、一つでも基準を満たさない項目があればその場で不合格となります。その場合、問題箇所を自分で整備するか、近くの整備工場に駆け込んで修理してもらい、再度検査を受け直すという手間が発生します。現代のボルボは電子制御も多く、目視だけでは判断できない不具合も潜んでいる可能性があるため、相応の覚悟と自己責任が求められる方法と言えるでしょう。
意外と重要?代車サービスの有無

車検で数日間、車を預けることになった場合、通勤や家族の送迎などで車が使えないと困るという方は多いと思います。そういった場合に、意外と重要になってくるのが代車サービスです。
正規ディーラーの場合、車検を依頼すれば無料で代車を貸し出してくれることがほとんどです。しかも、代車がボルボの最新モデルや、自分が乗っている車種とは違うモデルであることもあり、新しい車の乗り心地を試せる良い機会になるかもしれません。これはディーラーならではの楽しみの一つとも言えます。
一方、民間の整備工場の場合は、お店によって対応が本当にさまざまです。無料で代車を用意してくれるところもあれば、1日あたり数千円の有料サービスとなっている場合、あるいはそもそも代車の用意がないという場合もあります。
車検の費用を比較する際には、見積もりの総額だけでなく、代車が無料か有料かという点も忘れずに確認することをおすすめします。もし有料であれば、その料金も車検にかかるトータルコストとして計算に入れることが、後から「思ったより高くついた」という事態を防ぐための賢いポイントになると思います。
満足のいくボルボの車検を受けよう
ここまで、ボルボの車検について、費用や依頼先、点検項目など、さまざまな角度から見てきました。どの方法を選ぶにしても、それぞれのメリットとデメリットを深く理解することが、最終的に満足のいく車検につながるのだと思います。
この記事で解説したポイントを参考に、ご自身のライフスタイルや予算、そして愛車との付き合い方に最も合った選択をしてください。
- 車検のタイミングは満了日の1ヶ月前からが一般的
- 総費用は車の状態や依頼先によって10万円~20万円以上が目安
- 費用は「法定費用」と「車検基本料・整備費用」に分かれる
- 法定費用(重量税、自賠責保険料、印紙代)はどこで受けても一律
- ディーラーではボルボ独自の安全システム等の点検も実施
- 正確な費用は必ず事前の車検見積もりで確認する
- 見積もりでは整備内容が必須か予防かを確認することが大切
- ディーラー車検は専門性と安心感が最大のメリット
- ディーラーでは純正パーツを使用し、車の価値を維持しやすい
- 民間車検はディーラーより費用を抑えられるのが最大のメリット
- 民間車検では社外品など安価な部品を選べる場合がある
- 民間車検を選ぶ際は輸入車の実績確認がおすすめ
- ユーザー車検は費用を最も安く抑えられる可能性がある
- ユーザー車検は手間と時間、専門知識が必要な上級者向けの方法
- 代車サービスの有無や料金も依頼先を選ぶ上で重要なポイント
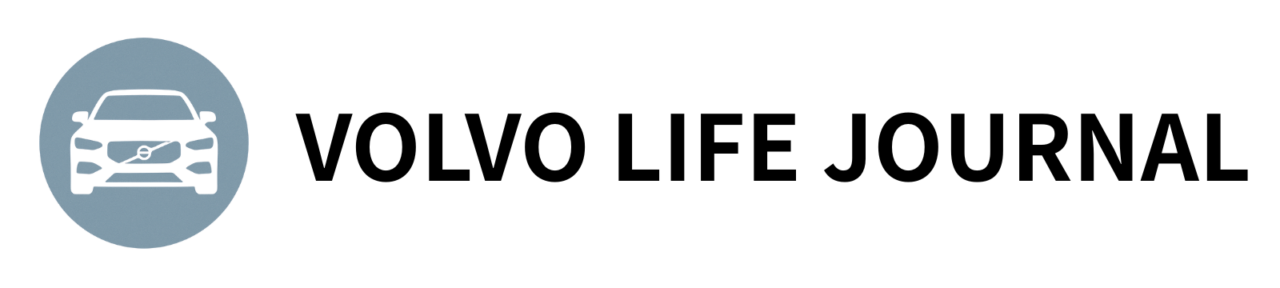

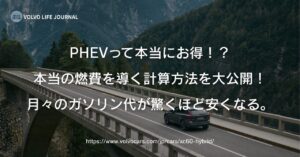

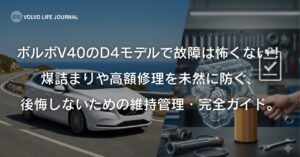
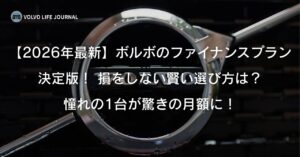
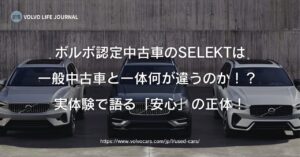


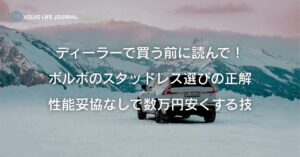
コメント