こんにちは、Tです。
「ボルボは頑丈」というイメージ、あなたも持っていませんか。
僕もV90に乗る前はもちろん、クルマに興味を持ち始めた子供の頃から、なんとなくそう思っていました。「ボルボ=安全」というイメージと強く結びついていますよね。
でも、それって具体的にどういうことなんだろう? なぜ、多くの人がボルボに対して「頑丈」という印象を持つのでしょうか。
僕もV90に乗っていた頃、ドアを閉めた時の重厚な音や、高速道路を走っている時のビシッとした安定感に触れるたび、「あぁ、守られているな」と感じたものです。
この記事では、僕がオーナー時代に感じた実感も交えながら、なぜボルボが「頑丈」と評価されるのか、その理由を歴史や設計、そして実際の走行性能から深掘りしてみたいと思います。
- ボルボが頑丈と言われる歴史的な背景がわかる
- ボルボ独自の「安全ボディ」の具体的な仕組みがわかる
- 客観的な衝突試験でどう評価されているかがわかる
- 頑丈さが実際の走行性能にどう影響するかがわかる
なぜボルボは頑丈と評価されるのか

- 「頑丈」と言われる歴史的な理由
- 思想が息づくボルボの安全ボディ
- 厳しい衝突試験評価が示す実力
- 高い耐久性を支える設計思想
- 長寿命車としての側面も持つのか
- 故障の少ない部品へのこだわりとは
「頑丈」と言われる歴史的な理由

ボルボの「頑丈」というイメージは、一朝一夕に作られたものではないですよね。
それは、ボルボという会社が創業当初からずっと持ち続けている、「安全はすべての人に平等であるべき」という深い哲学に基づいているんだと思います。
一番有名なエピソードは、やはり1959年の「3点式シートベルト」の発明です。今では当たり前の装備ですが、これを世界で初めて標準装備したのがボルボでした。
さらに驚くのは、ボルボがこの非常に重要な発明の特許を、無償で他のすべての自動車メーカーに公開したことです。
自社の利益よりも、社会全体の安全性を優先したわけですね。
こういうエピソードを知ると、ボルボというブランドへの信頼感がぐっと高まります。
また、昔の240シリーズなどが「空飛ぶレンガ」なんて呼ばれていたのも、その質実剛健でカクカクした、いかにも頑丈そうなデザインから来ています。こうした歴史の積み重ねが、今の「頑丈なボルボ」というイメージを形作っているんだと感じます。
ボルボ公式の安全に関するページはこちら
思想が息づくボルボの安全ボディ

ボルボの頑丈さを具体的に体現しているのが、その「安全ボディ」の構造です。
これは単に「硬い」というだけではなく、「どうすれば乗員を効果的に守れるか」を徹底的に考え抜いた設計思想の表れですね。
中心にあるのは「セーフティケージ」という考え方です。
万が一の衝突時でも、乗員がいるスペース(キャビン)が潰れてしまわないように、非常に硬い素材でカゴのように保護する構造になっています。
このセーフティケージには、「超高張力鋼板(ボロン鋼)」という、一般的な鋼板の何倍も強度がある特別な素材が惜しみなく使われています。
僕が乗っていたV90も、ドアがすごく分厚くて重かったんですが、それはこの頑丈なセーフティケージの一部だからなんですね。ドアを閉めた時の「ボスッ」という重たい音は、守られている安心感がありました。
一方で、クルマの前後(エンジンルームやトランク)は、「クラッシャブルゾーン」と呼ばれ、あえて潰れやすいように設計されています。
これは、衝突の瞬間にここが積極的に潰れることで衝撃エネルギーを吸収し、セーフティケージ(乗員室)へのダメージを最小限に食い止めるためです。
この「徹底的に硬く守る部分」と「あえて柔らかく潰れて衝撃を逃す部分」の絶妙な使い分けこそが、ボルボの安全思想の核であり、「頑丈さ」の秘密なんだと思います。
厳しい衝突試験評価が示す実力

こうしたボルボ独自の安全設計は、もちろん「感覚」だけの話ではありません。
客観的なデータとして、世界各国の公的な衝突試験で、常に最高ランクの評価を獲得し続けていることが、その実力を証明しています。
例えば、
- ヨーロッパの「ユーロNCAP」
- アメリカの「IIHS(米国道路安全保険協会)」
といった組織が行うテストですね。
特にアメリカのIIHSは、スモールオーバーラップ(車体のごく一部だけをぶつける)など、現実の事故に即した非常に厳しい試験を行うことで知られています。
ボルボの各車種は、こうした難易度の高いテストでも安定して「トップセーフティピック+(プラス)」という最高の評価を受け続けています。
僕がV90を選んだ理由の一つも、やはりこの客観的な「お墨付き」がある安心感でした。
自分自身はもちろん、大切な妻や友人を乗せるクルマとして、こうした信頼できるデータがあることは、何物にも代えがたい価値があると感じます。
高い耐久性を支える設計思想
ボルボの「頑丈さ」には、衝突安全性だけでなく、「長く乗り続けられる」という意味での耐久性も含まれていると思います。
これは、ボルボが生まれたスウェーデンの厳しい自然環境と、決して無関係ではないでしょうね。
スウェーデンといえば、冬が長く、寒さも厳しく、雪道では融雪剤(塩化カルシウムなど)を大量に撒くことで知られています。
こうした過酷な環境でもクルマが本来の性能を発揮し、長く乗り続けられるように、ボルボは昔から基本的な耐久性をとても重視してきました。
例えば、ボディの防錆対策や塗装の品質です。
ボルボの塗装って、なんだか独特の厚みがあって、しっとりとした深みを感じませんか? 僕もV90のマジックブルーメタリックの塗装が大好きでしたが、あれも単に美しいだけでなく、厳しい環境からボディを守るための耐久性を考えてのことかもしれません。
もちろん、最近のモデルが昔のクルマのように「絶対に壊れない」というわけではありません。
それでも、クルマの骨格となる基本部分が非常に真面目に、頑丈に作られている。それが高い耐久性の土台になっているんだと思います。
長寿命車としての側面も持つのか

https://www.volvocars.com/jp/cars/legacy-models/960-estate/
前述の通り、ボルボは長寿命なクルマとしても知られています。
街中でも、960や850といった、いわゆる「ネオクラシック」なボルボが今でも元気に走っている姿を見かけることがありますよね。
ああいうクルマが大切に乗られているのを見ると、なんだか嬉しくなります。
海外では「走行距離100万マイル(約160万km)達成!」といったニュースが話題になることもあり、基本的な設計がいかに頑丈であるかを示しています。
もちろん、僕が乗っていたV90のような現代のボルボは、高性能なセンサーや複雑な電子制御システムをたくさん搭載しています。
そのため、昔のシンプルなクルマと全く同じように「機械的に壊れない」とは言い切れない部分もあります。
それでも、クルマの「骨格」や「心臓部」がしっかりしているからこそ、適切なメンテナンスを続けていけば、本当に長く付き合っていける可能性を秘めているクルマだと感じます。僕もV90、本当はずっと乗り続けたかったですね…。
故障の少ない部品へのこだわりとは
「ボルボは故障が少ないですか?」と聞かれると、これは正直、少し返答に悩みます(笑)。
というのも、先ほども触れたように、最近のボルボは非常に多くの先進技術やセンサー類を搭載しているからです。
僕のV90は幸いセンサー類やSENSUSの不具合はありませんでしたが、ステアリングスイッチの故障やセルモーターの故障はありました。。
これはボルボに限らず、現代のヨーロッパ車全般に言えることかもしれませんが、こうした電装系の細かなトラブルは、国産車と比べると少しデリケートな面があるかもしれません。
ただ、ボルボがこだわっている「頑丈さ」や「信頼性」は、おそらくそこではないんだと思います。
ボルボが重視しているのは、クルマが「走る・曲がる・止まる」という、安全に走り続けるための根幹に関わる部分の信頼性ではないでしょうか。
エンジンやトランスミッション、ブレーキシステム、足回りといった基本的な部品は、非常に高い基準で設計・製造されていると感じます。
小さなトラブルはあっても、走行不能になるような致命的な故障は徹底して防ぐ。安全に関わる重要な部品には絶対に妥協しない。それがボルボの「故障」に対する考え方であり、頑丈さへのこだわりなのかもしれませんね。
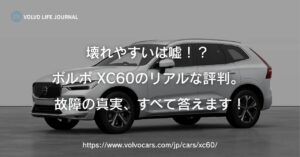
走行性能から見るボルボの頑丈な作り

- 優れた高速安定性が生む安心感
- 雪道走行性能で発揮される強さ
- ボルボSUVの強みと走破性
- ボルボが頑丈であることの総括
優れた高速安定性が生む安心感

ボルボの「頑丈さ」は、実際にハンドルを握って、特に高速道路を走ってみると本当によく分かります。
とにかく、まっすぐ走る安定感が抜群に高いんです。
これは、ボディ剛性(車体のねじれにくさ)が非常に高いため、速度が上がってもクルマがビシッと安定し、余計な揺れやブレが発生しにくいためですね。
僕が乗っていたV90 T6 AWDは、まさにそのお手本のようなクルマでした。
V90が採用している「SPA(スケーラブル・プロダクト・アーキテクチャ)」というプラットフォーム(車台)が本当に優秀で、まるで路面に吸い付いているかのように、どっしりと安定して走ってくれます。
特に雨の日の高速道路なんかは、AWDシステムとこの頑丈なボディのおかげで、不安を感じたことがほとんどありませんでした。
ボディがしっかりしていると、サスペンションも設計通りに正確に動いてくれるので、路面の凹凸を乗り越えた時も「ドンッ」という硬い衝撃ではなく、「トンッ」としなやかにいなしてくれます。
だから乗り心地もフラットで快適ですし、長距離を運転しても疲れにくい。この疲れにくさこそが、頑丈なボディがもたらす「安全」と「安心感」の証拠なんだと思います。
雪道走行性能で発揮される強さ

ボルボの本領が発揮されるシチュエーションといえば、やはり雪道かもしれません。
ご存知の通り、ボルボは北欧スウェーデンのメーカーです。冬は長く、雪も多い。そんな厳しい環境でクルマが作られているわけですから、雪道に強いのは当然とも言えます。
もちろん、高性能なAWD(四輪駆動)システムの恩恵も大きいです。
ボルボのAWDは、路面状況を瞬時に判断して、最も効率よくパワーを路面に伝えられるよう、前後左右のタイヤにトルクを自動で配分してくれます。
でも、それだけではありません。
滑りやすい雪道では、クルマの基本性能、つまり「頑丈なボディ」が何より重要になります。ボディがしっかりしているからこそ、AWDシステムやトラクションコントロール(タイヤの空転を防ぐ機能)が効果的に働き、ドライバーは安心してハンドル操作に集中できるんですね。
僕自身はV90で本格的な豪雪地帯を走る機会は多くありませんでしたが、冬の冷たい雨で濡れた高速道路や、凍結が心配な早朝の山道などでは、このAWDシステムと頑丈なボディがしっかり仕事をしてくれている実感を何度も味わいました。
雪国にお住まいの方にボルボオーナーが多いのも、こうした厳しい環境下での圧倒的な信頼性の高さからなんでしょうね。
ボルボSUVの強みと走破性

最近のボルボといえば、XC90、XC60、XC40といったXCシリーズに代表されるSUVが、世界的に大人気です。
僕が乗っていたのはV90というワゴンタイプでしたが、これらのSUVモデルも、ボルボならではの「頑丈さ」が大きな強みになっています。
もちろん、ジープのラングラーのような、岩場をガンガン走るための本格的なオフロード車とはキャラクターが違います。
ボルボのSUVは、あくまで「オンロード(舗装路)での快適性と安全性を最優先」しつつ、いざという時の走破性も備えている、というバランスが絶妙なんです。
最低地上高(地面との隙間)がワゴンやセダンよりも高く設定されているため、キャンプ場のちょっとしたデコボコ道や、大雪の日のわだちなどでも、安心して走破できます。
そして何より、これらのSUVも、V90などと同じく非常に頑丈なボディ構造をベースに作られています。
普通、車高が高いSUVは、カーブなどでグラっと傾きやすい傾向がありますが、ボルボのSUVはボディが頑丈なおかげでその不安定さが少なく、街乗りから高速道路まで、ワゴンやセダンに近い感覚で快適に、そして安心して走れるのが最大の魅力だと思います。
デザイン性と実用性、そして安全性を高いレベルで両立しているのが、ボルボSUVの強みですね。
ボルボが頑丈であることの総括
ここまで、ボルボがなぜ「頑丈」と言われるのかについて、僕の経験も交えながら見てきました。
最後に、ボルボの頑丈さについてのポイントをまとめておきます。
- ボルボの頑丈さは「安全は平等であるべき」という創業哲学が原点
- 1959年の3点式シートベルト発明と特許無償公開はその象徴
- 「セーフティケージ」という乗員室を硬く守る構造が核
- ボディには「超高張力鋼板(ボロン鋼)」という特殊な素材を使用
- 前後はあえて潰れる「クラッシャブルゾーン」で衝撃を吸収
- この「硬さ」と「柔らかさ」の使い分けがボルボの安全思想
- ユーロNCAPや米IIHSなど世界の衝突試験で常に最高評価
- スウェーデンの厳しい環境が「耐久性」も高めた
- 防錆対策や塗装の品質にも昔から定評がある
- 昔の240などは長寿命車として今も現役で走っている
- クルマの「骨格」が頑丈だから長く乗れる土台がある
- 電装系は国産車よりデリケートな面もあるかもしれない
- エンジンなど「走る・曲がる・止まる」の根幹部品は信頼性が高い
- 頑丈なボディは「高速安定性」に直結する
- 僕が乗っていたV90(SPA)の安定感は抜群だった
- 長距離運転が疲れにくいのも頑丈なボディのおかげ
- 雪道での安定性も、AWDと頑丈なボディが支えている
- SUVモデルも頑丈な基本骨格が強みになっている
ボルボの「頑丈さ」は、単に鉄板が厚いとか、壊れにくいという単純な話ではなく、乗員を守るための安全思想、厳しい環境で培われた耐久性、そして走行安定性という、クルマの根幹すべてに関わる深い哲学から来ているんだと、改めて感じます。
だからこそ、多くの人がボルボに「安心感」と「信頼」を寄せるんでしょうね。
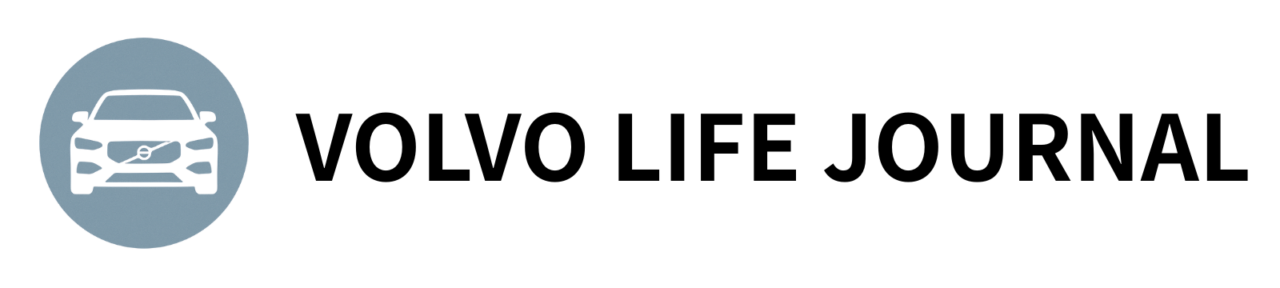
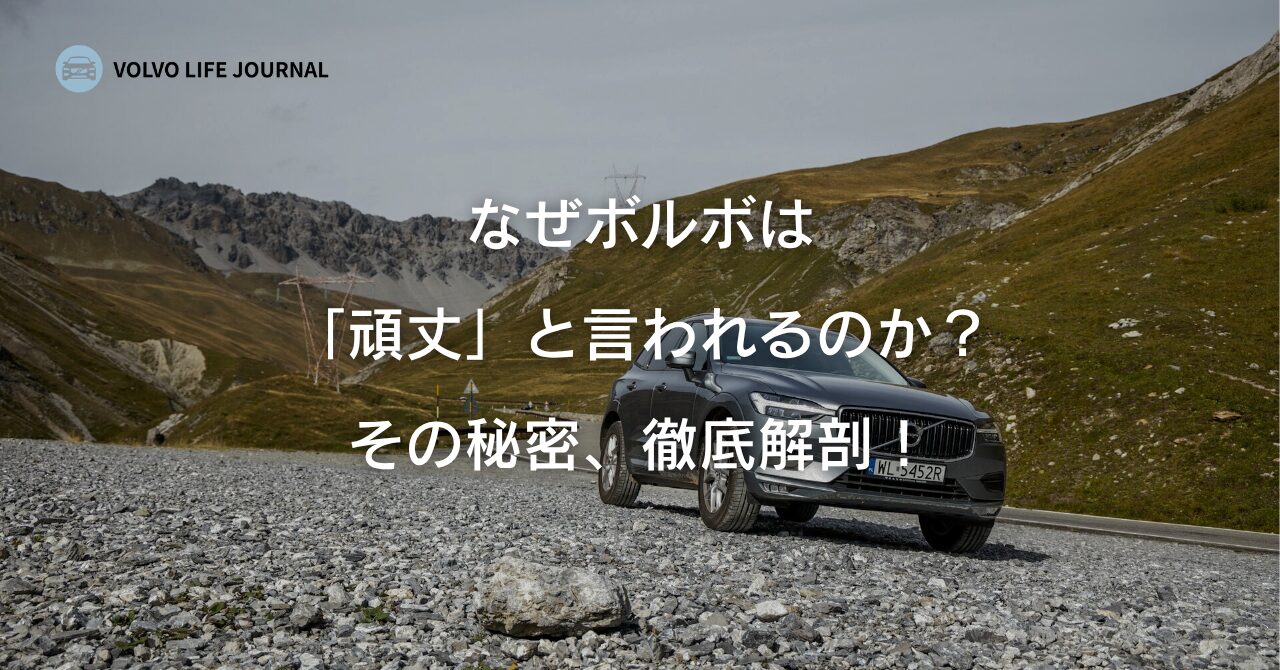

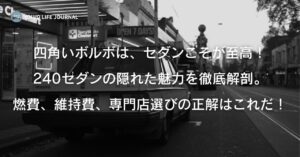
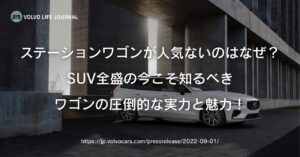
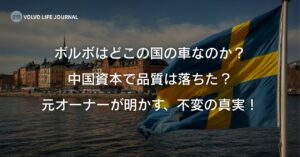
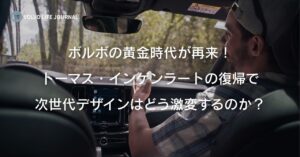
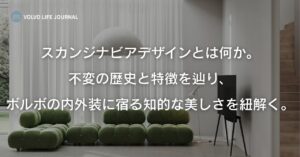
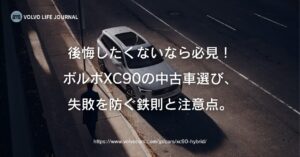
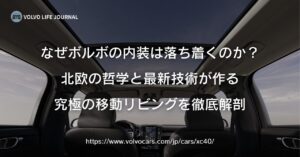
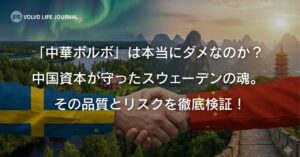
コメント